ブログ記事のまとめってどんな役割があるのかな?あと、どうやって書けばいいのかも知りたい。
こんな疑問にお答えします。
- ブログ記事のまとめとは
- ブログ記事のまとめの役割
- 記事のまとめの書き方のポイント
この記事を書いている僕はSEO歴4年。またWeb資格でSEO検定を全級保有しています。それらの経験をもとに解説していきます。
ブログ記事のまとめとは、記事の最後の見出しで、記事全体の内容を簡潔に要約する文のことですね。
まとめは必須ではないですけど、あった方が読者満足度は高まるかなと。記事を最後まで読んでいると、内容を忘れてしまうことがあるからですね。
まとめを工夫することで、記事の価値を底上げすることができますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
ブログ記事のまとめの役割

まとめの役割は大きく分けると2つです。
- ユーザー満足度を高める
- SEO効果を高める
ユーザー満足度を高める
読者は記事を読んで「知りたい情報を得られた」と感じたいものです。
そのため、記事の最後に要点を整理して示すことで、満足感が高まります。
特に長文の記事では、全体を振り返るまとめがあることで、「この記事は役に立った」と思ってもらえる可能性が高まります。
たとえば、複雑な内容を扱う解説記事の場合、最後に重要なポイントを箇条書きで整理すると、読者の理解が深まりやすくなります。
結果的に、読者の信頼を得てリピート訪問やシェアに繋がります。
記事内容の理解度が高まる
記事の内容を深く理解してもらうためには、重要なポイントを再度整理することが効果的です。
読者が「何が一番重要だったのか」を把握できるようにすることがポイントです。
例えば、専門的な知識が多い記事では、まとめ部分に主要な用語や概念を簡潔に説明すると、初心者にも分かりやすい記事に仕上がります。
さらに、まとめ部分に補足情報をリンクすることで、理解を助ける手段としても活用できますよ。
記憶に定着できる
人は繰り返し目にする情報を覚えやすい傾向があります。
記事の最後に要点をまとめると、内容が記憶に定着しやすくなります。
例えば、
- 学習系の記事では、重要な情報を短く箇条書きにする→記憶に残りやすくなる
- 「勉強を効率化する3つのステップ」として具体例を挙げる→読者は手順を覚えやすくなり、実生活で活用できるようになる
上記のイメージですね。
行動を後押しできる
まとめ部分で読者に次の行動を提案することで、記事をより有効活用してもらえます。
具体的な行動提案は、読者にとって非常に役立ちます。
例えば、
- 「この記事で紹介した方法を試してみてください」
- 「関連する記事もチェックしてみてください」
といった提案を行うと、読者が迷わず行動に移ることができます。
さらに、商品のレビュー記事では、「今すぐ購入はこちら」とリンクを提示することで、購買行動を促す効果も期待できますよ。
広告へ誘導できる
記事の最後に広告やプロモーションを配置する場合、まとめ部分を活用することで読者の関心を引きつけやすくなります。
まとめが読者に有益であるほど、その後に続く広告にも好印象を与えやすくなります。
たとえば、
- 「この記事で紹介した商品はこちらから購入できます」
- 「とりあえず無料カウンセリングでいろいろ相談してみてください」
というリンクを設置することで、自然な形で広告へ誘導できます。
また、関連する商品のバナーを設置することでクリック率を向上させる効果もあります。
SEO効果を高める
まとめ部分に適切なキーワードを自然に散りばめることで、SEO対策にも効果を発揮します。
例を挙げてみます。
- 「初心者向けブログ運営」
- 「簡単にできるSEO対策」
といった検索されやすい言葉を活用すると、検索エンジンからの評価が高まり、アクセス数が増える可能性があります。
また、関連キーワードを含む文章を追加することで、記事のテーマに沿った内容を強調することができ、読者にも検索エンジンにも分かりやすい構造を作り出せます。
独自の感想を書いて独自性を高められる
まとめ部分に筆者独自の視点や感想を加えることで、記事に個性が生まれます。
他の記事では触れられていない具体的な意見や体験談を盛り込むことで、読者に新鮮さを感じてもらうことができます。
例えば、旅行記事で「この場所は実際に行ってみると、期待以上の魅力がありました」といった感想を述べることで、他の記事との差別化を図ることが可能です。
こうした個人的な意見は、読者との親近感を深めるためにも有効です。
滞在時間の上昇
記事の最後まで興味を引きつける内容を提供することで、読者がページにとどまる時間を延ばすことができます。
滞在時間が長いと検索エンジンからの評価も向上し、記事全体の価値が高まります。
例えば、「この記事のポイントをもう一度簡潔に振り返りましょう」という形で読者の注意を引きつけると、最後まで読み進めてもらいやすくなります。
内部リンクへ誘導し離脱率を減らせる
まとめ部分に関連する内部リンクを設置することで、読者が別の記事に移動しやすくなります。
内部リンクを活用することで、サイト全体の回遊率が向上し、離脱率を下げる効果が期待できます。
例えば、「この記事に関連する情報は以下の記事で詳しく解説しています」というリンクを設置すると、読者の興味を引き続き引きつけることができますよ。
ブログ記事のまとめの書き方のポイント
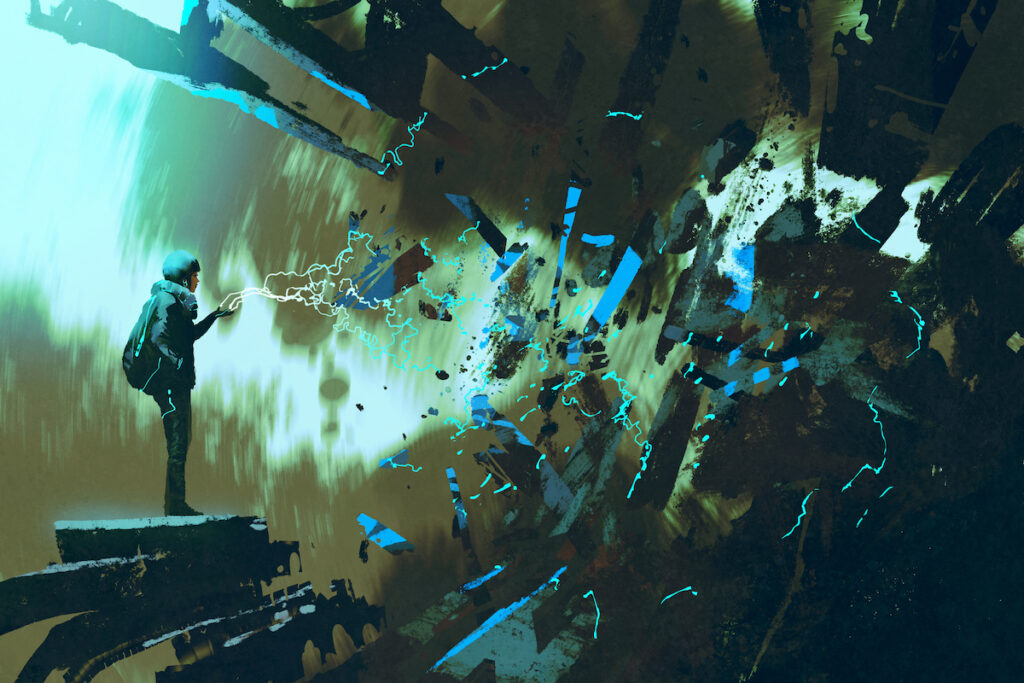
まとめの書き方のポイントを解説していきますね。
記事の内容を簡潔にまとめる
まとめ部分では、記事全体の内容を短く整理することが大切です。
特に長文の記事では、主要なポイントを抜き出して簡潔に伝えることで、読者が内容を把握しやすくなります。
具体的には、「この記事では以下の3つのポイントについて解説しました」といった形でまとめると、読者にとって理解が容易になります。
また、簡潔なまとめは、忙しい読者にも好まれる特徴があります。
要点を箇条書きする
箇条書きは視覚的に情報を整理しやすく、読者にとってわかりやすい形式です。
たとえば、以下のように箇条書きで要点を整理します。
- ポイント1:記事の概要
- ポイント2:具体的な解決策
- ポイント3:次に取るべき行動
この形式を使うことで、読者が内容をスムーズに理解できます。
また、箇条書きはSEOにも効果的で、要点が検索エンジンに認識されやすくなります。
キーワードを入れる
まとめ部分に主要なキーワードを盛り込むことで、記事のSEO効果を高めることができます。
たとえば、
- 「初心者向け」
- 「簡単にできる」
- 「具体的な手順」
などの言葉を活用することで、検索エンジンからの評価が向上します。
さらに、キーワードを自然な形で文章に組み込むことで、読者にも検索エンジンにも好まれるコンテンツを作ることが可能です。
独自の意見や感想を書く
筆者の意見や感想を盛り込むことで、記事に独自性を加えられます。
たとえば、「私はこの方法を実践してから、効率が大幅にアップしました」といった個人的な体験を加えると、記事がより魅力的になります。
独自の感想を入れることで、読者は筆者に共感を抱きやすくなり、記事全体の信頼度が向上します。
読者に次のアクションを促す
まとめ部分で具体的な次のアクションを提案すると、読者が記事をより活用できます。
例を挙げるなら、「この記事で紹介した手順を実際に試してみましょう」といった提案を行うと、読者の行動を促進できます。
また、「詳しい情報は以下のリンクをご覧ください」といった形で内部リンクを活用することも有効です。
文章と共に内部リンク先へ誘導
まとめ部分で関連する内部リンクを提示することで、読者の興味を引き続き引きつけられます。
例えば、「他の役立つ情報は以下の記事で詳しく説明しています」という形でリンクを設置すると効果的です。
また、内部リンクを設置することで、サイト全体の評価も向上します。
広告へ誘導
まとめ部分を活用して広告や商品ページへのリンクを設置することも可能です。
たとえば、「この記事で紹介した商品はこちらから購入できます」とリンクを設けると、広告効果を高めることができます。
また、読者が興味を持ちやすいように、記事内容と関連性の高い広告を選ぶことが重要です。
再度本文へ誘導
まとめ部分で本文内の重要なセクションに再び誘導することで、読者が必要な情報を再確認しやすくなります。
たとえば、「詳しい手順については本文のこちらのセクションを再確認してください」と案内すると効果的です。
また、読者が興味を持った箇所をすぐに見直せるような工夫も有効です。
ブログ記事のまとめの例文

例文もご紹介しますね。
例文1:ノウハウ記事
この記事では、初心者向けのブログ運営のポイントを解説しました。要点を以下にまとめます。
- 初心者に最適なテーマ選び
- 読者の課題を解決する内容作り
- SEO対策を意識した記事構成
これらのポイントを押さえることで、初心者でも効果的なブログ運営が可能です。ぜひ参考にしてみてください。
例文2:レビュー記事
この記事では、人気のスマートフォンをレビューしました。以下がまとめです。
- デザイン性と使いやすさの両立
- 高性能なカメラ機能
- バッテリー持続時間の課題
総合的に見て、価格に見合う価値のあるスマートフォンです。購入を検討している方にはぜひおすすめします。
例文3:まとめ記事
この記事では、おすすめの旅行先を10か所紹介しました。以下がその要点です。
- 自然を満喫できるスポット
- 歴史と文化を楽しめる場所
- リラックスできるリゾート地
自分の好みに合った旅行先を選んで、素晴らしい時間をお過ごしください。
ブログ記事のまとめを書く際の注意点

注意点を守りながらまとめを書くことで、記事全体の品質を高め、読者により良い情報提供ができます。
具体的なポイントを一つひとつ詳しく見ていきましょう。
長文になりすぎない
まとめ部分は簡潔にまとめることが重要です。
長文になりすぎると読者が内容を把握しづらくなり、離脱する原因になります。
まとめは読者が記事の要点をすばやく確認できるセクションです。ここが長すぎると、逆に読者がどの情報が重要か分からなくなり、記事全体の価値が下がる可能性があります。
また、短くても的確な情報が伝われば読者の満足度は高まります。
具体例
例えば、5000文字に及ぶ解説記事のまとめ部分で、要点をさらに1000文字使って書いてしまうと、読者は疲れてしまいます。
一方で、200–300文字に要点を整理して書けば、読者が効率よく内容を理解でき、満足感を持って次の行動に移りやすくなります。
まとめは200–300文字程度に収め、簡潔にポイントを伝えましょう。それだけで読者にとって分かりやすい記事となります。
“いかがでしたか?”は書かない
「いかがでしたか?」のような曖昧な表現は避け、読者に明確な行動や次のステップを提案しましょう。
曖昧なフレーズでは、読者に具体的な価値を提供したり行動を促したりする力が弱いからです。
代わりに、次の行動を指示することで、記事の目的を達成しやすくなります。
具体例
例えば、ブログのまとめ部分で「いかがでしたか?」と書く代わりに、
- 「この記事の方法を試して、さらに効果を実感してみてください」
- 「次に役立つ情報はこちらの記事で詳しく解説しています」
と書けば、読者が迷うことなく行動できます。
読者に具体的な提案を示すことで、記事の効果を高めることができます。
「いかがでしたか?」ではなく、明確で有益なメッセージを送りましょう。
共感できる内容を書く
読者が共感できる内容を心がけることで、記事全体の親しみやすさが向上します。
共感を生む表現は、読者が筆者の考えに納得しやすくし、記事に対する信頼感を高めます。
特に、自分ごととして受け止められる内容は、読者の興味を引きつけやすいです。
具体例
例えば、「忙しい毎日でも実践できる簡単な節約術」という記事で、
「私自身、家計簿が続かない日々がありましたが、今回の方法を試してみたところ、とても簡単で続けやすかったです」
と書けば、多くの読者が共感できます。
共感できる内容を取り入れることで、読者との距離を縮め、記事全体の魅力を高めることができます。
本文と違う内容を書かない
まとめ部分では、本文と一致した内容のみを書き、矛盾が生じないように注意しましょう。
読者がまとめを読んで本文と矛盾を感じると、記事全体の信頼性が損なわれます。一貫性のある情報提供が、読者に安心感を与えます。
例えば、ダイエット記事の本文で「1日30分の運動が重要」と解説しておきながら、まとめで「運動は不要」と書くと読者は混乱します。まとめ部分では本文の要点を正確に反映し、簡潔に整理することが必要です。
本文と一致する内容だけを使い、読者が安心して情報を受け取れるようにしましょう。
記事に書いていないことを書かない
まとめ部分では、本文に書かれていない情報を新たに追加しないようにしましょう。
本文に書かれていない情報が突然現れると、読者は混乱し、記事全体の信憑性が低下します。
記事全体の流れを守ることが重要です。
具体例
例えば、レシピ記事で「材料はシンプルに3つだけ」と説明しておきながら、まとめ部分で
「その他に調味料を10種類使いました」
と新たに情報を追加すると、読者は混乱します。
まとめ部分は、本文の内容を正確に要約することに専念し、新しい情報を加えないようにしましょう。
まとめ

まとめ部分はブログ記事において重要な役割を果たします。
この記事で紹介したポイントを参考に、読者の満足度を高める効果的なまとめを作成してくださいね。
効果的なまとめは、記事の価値をさらに高める手段となり、読者との信頼関係を築く大きな助けとなりますよ。


